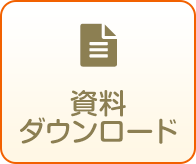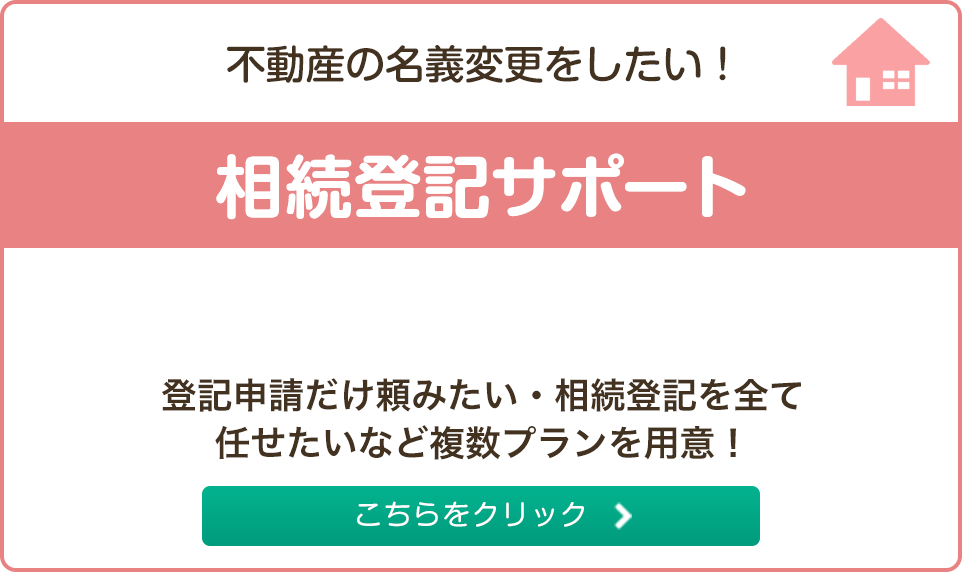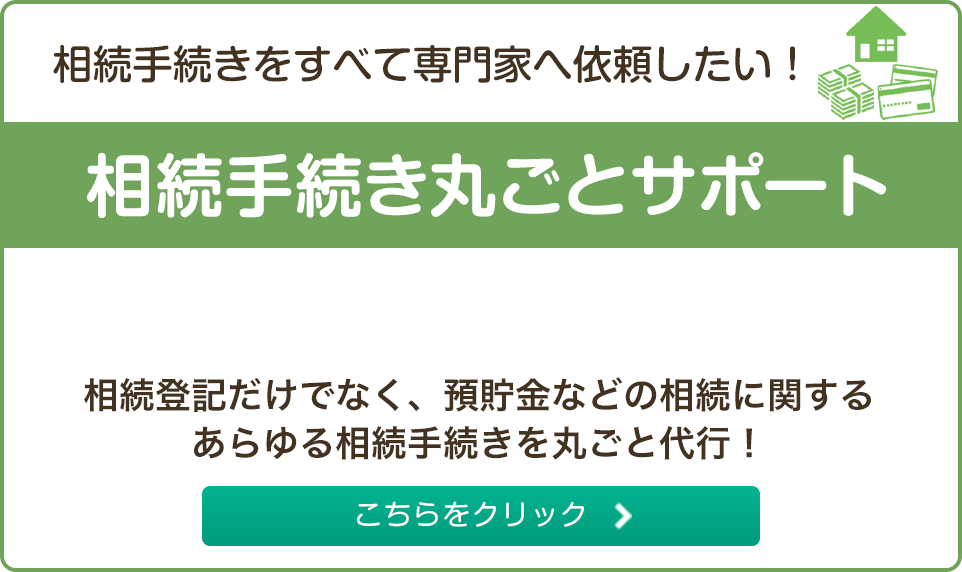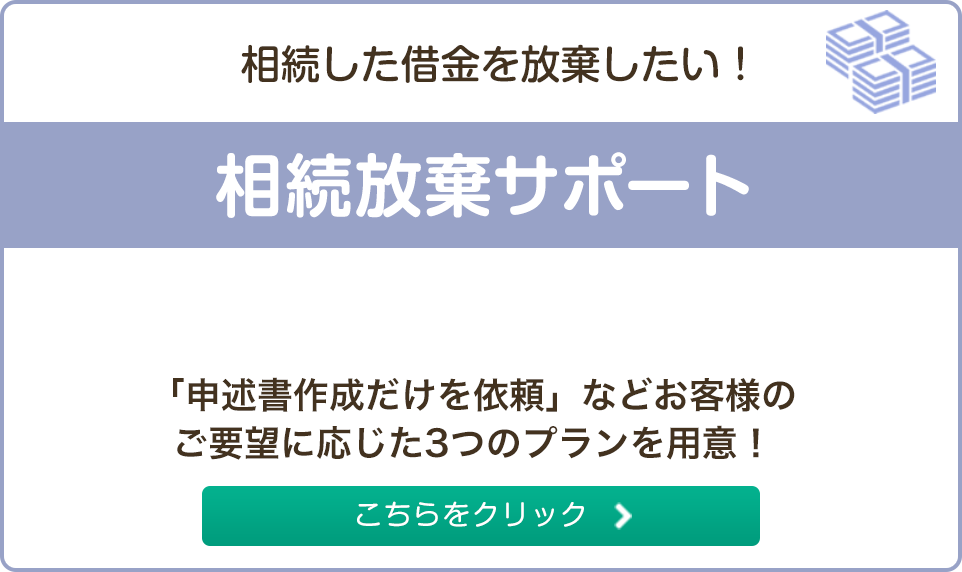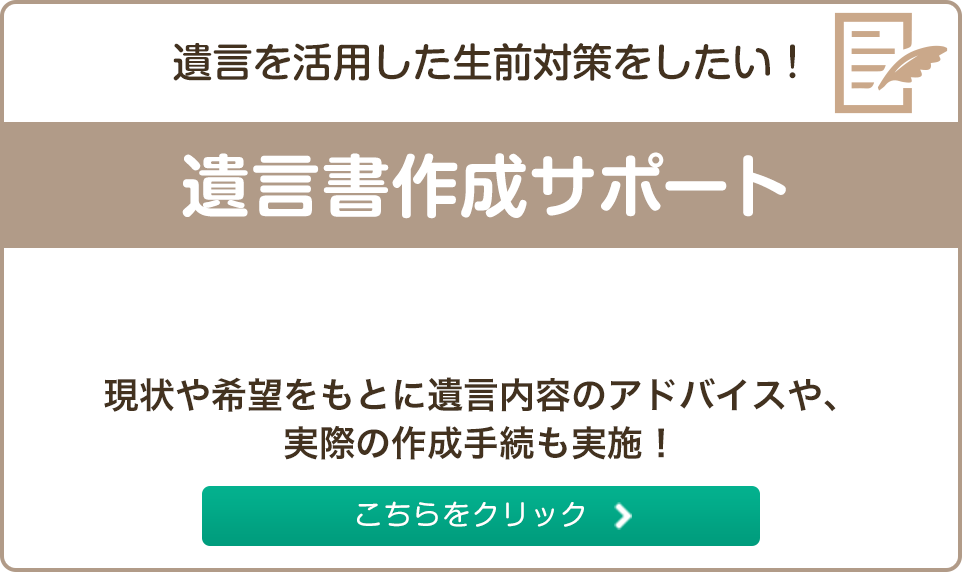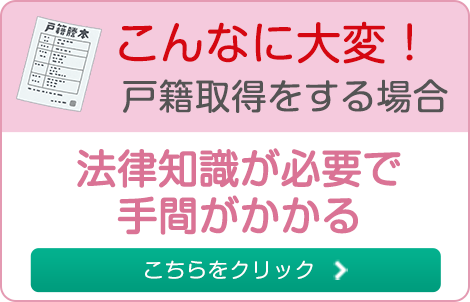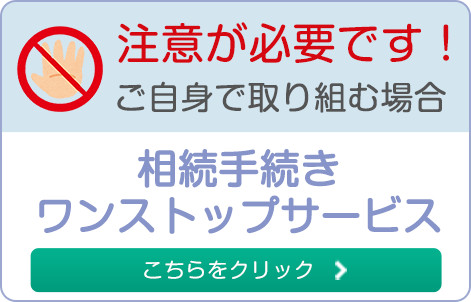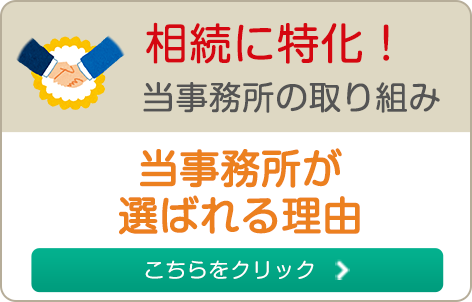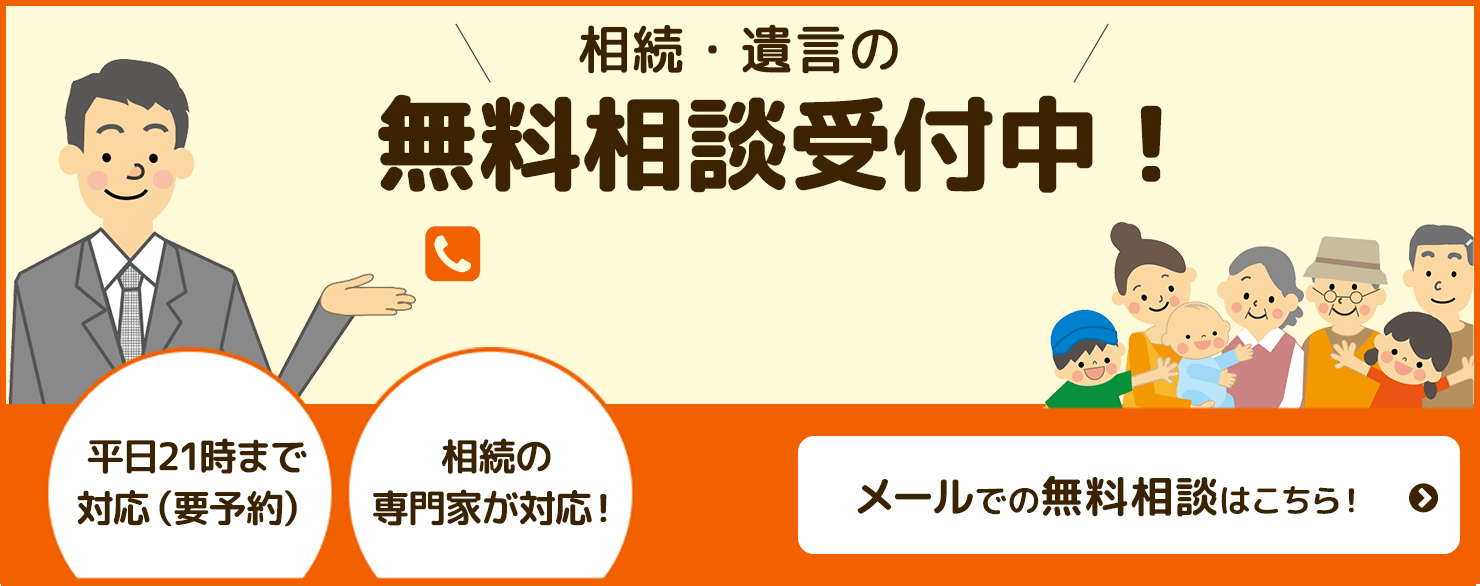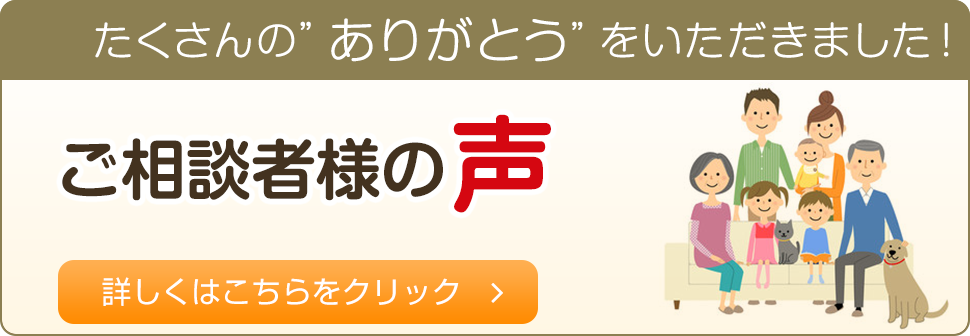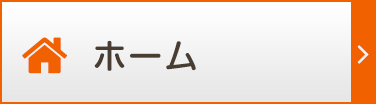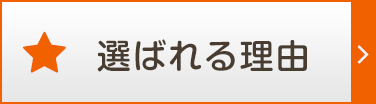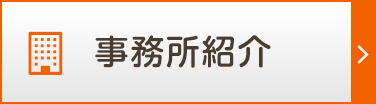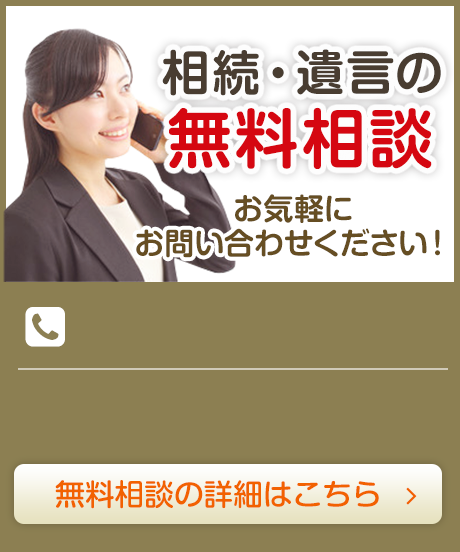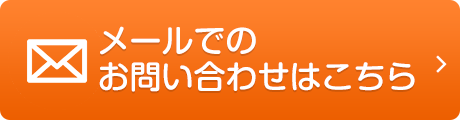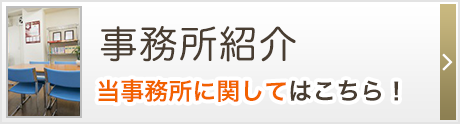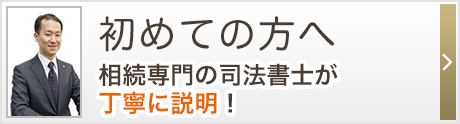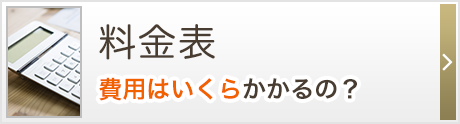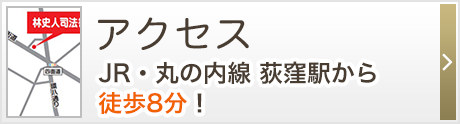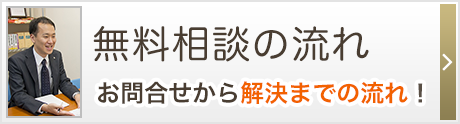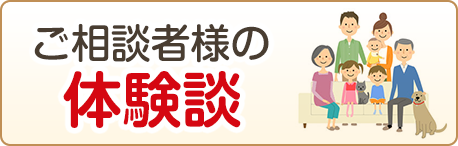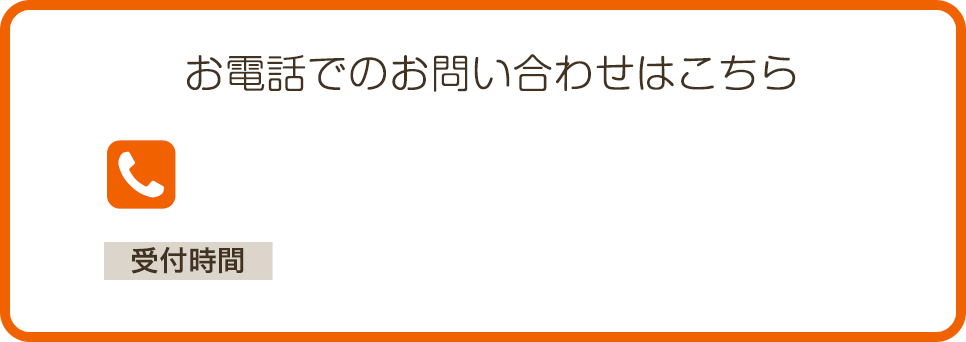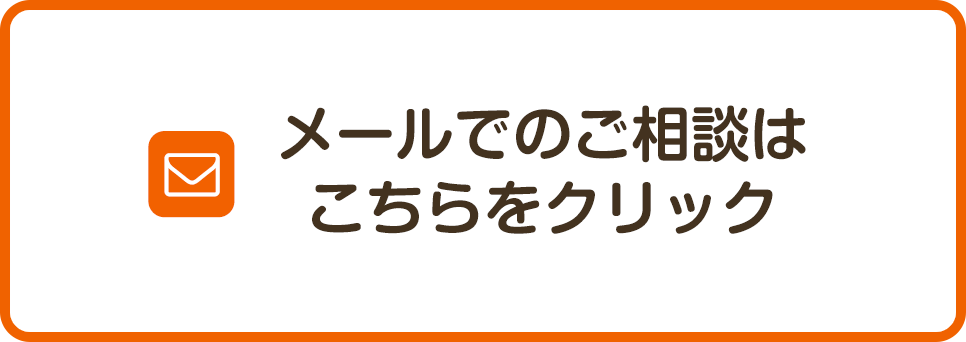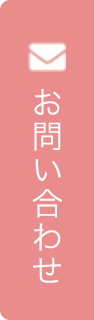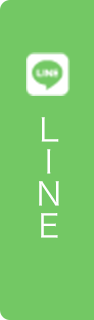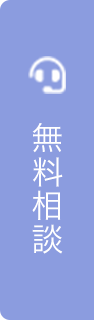杉並区荻窪で銀行預金の相続手続きでお困りの方に相続の専門家が分かりやすく解説
亡くなった方の名義になっている銀行預金は当然に「相続財産」です。
相続するためには、遺言書があれば原則的には遺言書に従って相続をし、遺言書がなければ複数の相続人がいる場合には誰がいくら相続するのか分配方法を相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
この記事では銀行預金の相続手続きについて、口座の凍結から払い出しまで、必要な書類についても詳しく解説します。
なお、相続手続きは複雑な場合がありますので、わからないことがあれば杉並・荻窪 相続遺言相談所(運営:林史人司法書士事務所)にお気軽に相談してください。
亡くなった方の預金口座は「凍結」される
原則として亡くなった方の預金口座は凍結されるため、相続人でも払い出しができなくなり、自動引き落としされていたクレジットカード等の支払いも中止されるので注意しましょう。
NHKの受信料や光熱費、電話料金なども亡くなった方の口座からの引き落としになっていれば凍結されたままでは引き落としされないため、サービスを受けられなくなってしまうおそれがあります。
銀行が口座を凍結するタイミング
口座が凍結されるのは銀行が預金口座の名義人が亡くなったことを知ったときからです。
基本的には相続人等からの届出がされることで銀行が知ることになります。
銀行に亡くなった方の預金を払い出しに行ったところ、本人確認の際に既に名義人本人は亡くなっていることを知られて凍結されることも多いです。
なお、死亡届を役場に提出しても役場から銀行に通知がされるようなことはありません。
凍結される前に払い出しをするリスク
それでは銀行に知られる前にキャッシュカードなどを利用して亡くなった方の預金口座から払い出しをすることもできそうですが、次のようなリスクがあるので避けた方がよいでしょう。
単純承認とみなされる
亡くなった後に相続財産となる預金口座から払いだすことで相続を単純承認したとみなされるおそれがあります。
後になって、亡くなった方に多額の借入があることがわかっても単純承認をしてしまうと「相続放棄」をすることができなくて負債を全て引き継ぐことになってしまいます。
相続人間でトラブルになるおそれがある
兄弟姉妹など複数の相続人がいるときには、預金をかってに引き出してしまうと「自分のために使ってしまった」などと憶測されて遺産分割協議をするときに不利になるおそれがあります。
また、相続人の中には勝手に自分のために相続預金を使ってしまう方がいないとはいえません。
預金口座が凍結されることでこのような不測の事態を防ぐこともできるでしょう。
亡くなった方の預金口座の凍結は、このようなトラブルに銀行がまきこまれないようにするための防御システムでもあるのです。
凍結された預金でも払い出しできる場合がある
亡くなった方の預金を利用して葬儀費用や亡くなった方の入院費用などを払いたいこともありますから、このような場合には遺産分割協議が終わっていないときにも利用できます。
遺産分割協議が整う前に払い出しをするときには、後日のトラブルを防ぐために引き出した金額や利用した目的と金額などは領収書などを保管しておきしっかりと説明できるように記録を残しておきましょう。
相続預金の払い戻し制度
以下の金額まで(上限は1銀行ごとに150万円)は遺産分割協議が終わっていなくても単独で払い戻しができます。
(相続預金額×法定相続分×1/3)
この場合の法定相続分は、払い戻しを請求する相続人がもっている相続できる法定割合です。
一般的には以下の書類が必要になりますが、銀行によって異なるため予め確認をしておくとよいでしょう。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本などとよばれるものを含みます)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを請求する方の印鑑証明書と実印
仮に父親が亡くなって母親と子ども二人(A、B)が銀行預金1,000万円を相続した場合にAが請求できる金額は次のように計算します。
Aの法定相続分は母と子がそれぞれ半分ずつ相続するのでAは4分の1(1/2×1/2・・母が2分の1、残りの2分の1を兄弟二人で半分ずつ)ですから、
1,000万円×1/4×1/3≒833,333円となります。
2,000万円だと(2,000万円×1/4×1/3≒1,666,666円)となりますが、実際に払い戻しできるのは150万円に制限されます。
仮処分を利用した払い戻し請求
家庭裁判所に申立てを行うことで、前記の制限を超える金額を遺産分割協議が整わなくても払い戻すことができます。
ただし、仮処分の申立てをするには遺産分割の調停や審判を求めることになるため、慎重に行いましょう。
凍結解除をする方法
凍結された預金口座の凍結を解除するためには、銀行に相続人を明らかにしたうえで、解約などの相続手続きを行うことになります。
銀行によって必要な書類が異なりますので、事前に持参する書類を電話などで確認しましょう。
最近では、銀行の本・支店の窓口で直接預金の相続手続きをするのではなく、本部で一括して相続手続きを取り扱う銀行が増えています。
まずはその銀行がどこで相続手続きを取り扱っているのかを確認しましょう。
遺言書がある場合
遺言書が残されている場合には次のような書類を準備します。
- 遺言書
- 遺言書によって指定された相続人の印鑑証明書
- 実印
- 遺言者(口座名義人=亡くなった方)の死亡記事がある戸籍謄本(抄本)
- 払い戻し請求者が指定された方であることがわかる資料(戸籍など)
- 本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認手続き」が必要なので注意しましょう。
ただし、自筆証書遺言でも法務局での「遺言書保管制度」を利用すれば検認手続きを省略できます。
また、遺言書で「遺言執行者」を指定していない場合には全ての相続人がわかる範囲の戸籍や相続人全員の印鑑証明書等を要求されることがありますので、事前に確認して準備しておくことをおすすめします。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、法定相続人が誰かを確定させ、そのうちの誰がいくら相続するかを明らかにする必要があります。
そのため、以下のような書類が必要になります。
- ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本などとよばれるものを含みます)
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員が記名押印した遺産分割協議書
- ・遺産分割協議書に押印された印鑑の印鑑証明書
- ・本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
複数の銀行に預金口座があるときには、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると戸籍謄本等を複数取得したり、コピーしたりする必要がなくなるので便利です。
|
法定相続情報証明制度とは 法務局に法定相続人の範囲がわかる戸籍謄本等を提出することで、法務局が法定相続人を証明してくれる制度で、無料で利用できます。 証明のための法定相続一覧図(家系図のようなもの)を作成して証明請求を行います。 法定相続一覧図に住所を記載しておけば住所も合わせて証明されます。 |
銀行の相続手続書類には原則として一連の用紙に相続人全員が記名押印することになります。
そのため、相続人が複数いる場合には書類が煩雑になりがちです。
相続人が複数いるときには、たとえ法定相続分で預貯金を分配するときでも一旦は相続人のうちの一人が単独で相続する内容の遺産分割協議書を作成し、相続手続後に分配する方法をとるとスムーズに手続きをすることができます。
遺産分割協議書の記載が不十分だと「贈与税」がかかることもあるので、遺産分割協議書の作成には注意が必要です。
詳しい書類の作り方については、林史人司法書士までご相談ください。
相続人を特定するために必要な戸籍の範囲
今回の記事では相続人の範囲を特定するために必要な亡くなった方の戸籍について次のように表現しています。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本などとよばれるものを含みます)
具体的には、亡くなった方の出生から死亡まで「連続」した戸籍が必要です。
まず出生により親の戸籍に記載され、本籍を移す(転籍)と今までの本籍地の戸籍は「除籍」となり、結婚すると新しく夫婦単位で戸籍が編成されて親の戸籍からは「除籍」されます。
また、古くなったりコンピュータ化されたりすることで改製されることもあり、改製される前の戸籍を「改製原戸籍」とよびます。
全ての戸籍の記載事項を謄写したものを「謄本」、一部を謄写したものを「抄本」といい、コンピュータ化された戸籍では「全部事項証明書」「一部事項証明書」とそれぞれ表しています。
このように呼び方はいろいろと変わりますが、亡くなった方の相続人(特に子どもの有無)を確認するためには「出生から死亡まで、連続」した戸籍が必要になるのです。
あわせて亡くなった方については「他にいないこと」を証明するため、「抄本」ではなく「謄本」が必要なので注意しましょう。
戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まっています。
戸籍謄本等は原則として本籍地の役場で発行されるので、直接本籍地の役場に出向いて請求するか郵便で請求することになりますが、広域交付制度を利用すれば一か所の役場でそろえることができるので便利です。
広域交付制度にはいろいろな制限があるため全ての戸籍謄本を取得することはできないこともあります。
詳しい制度については林史人司法書士事務所までお問い合わせください。
まとめ
今回は、銀行預金の相続手続きについて解説しました。
銀行預金の相続手続きは、必要な戸籍の収集、銀行からの手続き書類の取寄せ、相続人間での話し合いなど、複雑で時間がかかる作業になりがちです。
そもそも身近な方が亡くなり自分自身が相続人になる機会が多くないのは当然で、機会がなければ手続きに不慣れなのは当たり前のことです。
そのような方のために、私ども林史人司法書士事務所では、銀行預金の相続手続きを実際に相続した方の立場にたって親身な相談対応を心がけております。
銀行預金の相続手続きで不安や困ったことがあれば、まず杉並・荻窪 相続遺言相談所(運営:林史人司法書士事務所)まで気軽にご相談ください。
杉並・荻窪 相続遺言相談所では相続の無料相談を実施中

杉並・荻窪 相続遺言相談所では相続手続きについて、初めての方や慣れない方にお気軽に相談していただきやすいように無料相談を実施しております。
無料相談の流れはこちら>>
お問い合わせは、お電話(平日9:00〜21:00)もしくはメール(24時間受付)よりご連絡下さい。
お電話>>03-5303-5356